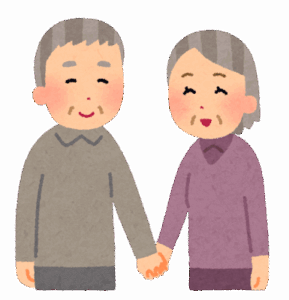遺産分割協議をしないとどうなる?司法書士が教える相続トラブルと対処法
遺産分割協議、きちんと行っていますか?
皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもと かいま)です。
ご家族や大切な方が亡くなられた後、様々な手続きに追われる中で、つい後回しになってしまいがちなのが「遺産分割協議」です。また、つい口約束で終わらせてしまっていませんか?
遺産分割協議は、後のトラブルを防ぐためにも、しっかりと書面に残しておくことがとても重要です。ここでは、遺産分割協議の基本と、行わなかった場合に起こり得るリスクについて解説します。
遺産分割協議とは?
遺産分割協議とは、亡くなられた方の財産(不動産・預貯金・動産など)を、相続人全員で話し合って分ける手続きです。
ポイントは「相続人全員の同意が必要」であること。誰か一人でも欠けると、その協議は無効となってしまいます。
遺産分割協議をしないと、こんなリスクがあります
1. 法定相続分でしか手続きができない
相続人が複数人いたり、遺言書がない場合、相続財産は相続人全員の共有財産となり、法定相続分に従って管理されます。預貯金などについては法定相続分に従って手続きを行うことが出来ます。しかし不動産を売却する際は、相続人全員の同意が必要です。ひとりでも反対すれば、売却等の手続きは行えません。
2. 遺産が共有状態になり、将来さらに複雑化する可能性
遺産が共有のまま次の世代に引き継がれると、共有者が増えてしまい、遺産分割協議がますます難しくなります。さらに、相続人の中に行方不明者が出てきた場合には、手続きが大幅に複雑化します。
また、相続人の一人が自身の持分を第三者に売却することも可能であり、結果として、相続に関係のない第三者が遺産の一部を所有する事態も起こり得ます。
3. 相続税の特例が使えず、負担が大きくなる
配偶者控除や小規模宅地等の特例など、相続税を軽減できる制度がありますが、これらは基本的に遺産分割協議が完了していることが条件です。協議が間に合わないと、多額の相続税を現金で納める必要が出てくる可能性があります。
遺産分割協議ができないときは?
意見がまとまらない、協力してもらえないといった場合には、家庭裁判所へ「遺産分割調停」の申し立てを行います。調停では中立な調停委員が間に入り、相続人が直接顔を合わせずに話し合いを進めることが可能です。調停を有利に進めるためにも、法律の専門家への相談をおすすめします。
相続人の中に行方不明者がいる場合
相続人のひとりが長らく連絡が取れない、所在が不明といったケースでは、家庭裁判所へ「不在者財産管理人」の選任を申し立てます。この管理人が不在者の代理として遺産分割協議に参加します。
おわりに
相続の手続きは感情も関わるため、つい後回しにされがちですが、遺産分割協議は相続の出発点とも言える大切な手続きです。
後々のトラブルを防ぐためにも、「口約束ではなく書面でしっかりと」「早めに専門家へ相談を」——これが円満な相続への第一歩です。
お困りのことがありましたら、お気軽に当事務所までご相談ください。
皆様のご事情に寄り添い、丁寧にサポートさせていただきます。