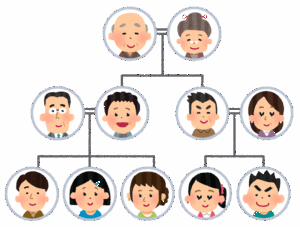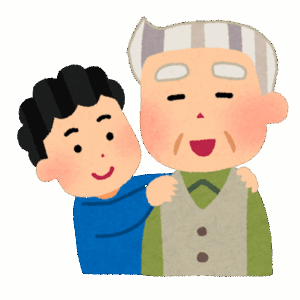借金を相続しないために|相続放棄の基礎知識について司法書士が解説
皆さま、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもと かいま)です。
相続と聞くと、不動産や預貯金といった「プラスの財産」を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、実際には「マイナスの財産」、つまり借金も相続の対象になります。
たとえば、「亡くなった方に借金があった」「金遣いが荒かったので借金があるかもしれない」といった不安をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。そんなときに活用できるのが「相続放棄」という制度です。
「相続放棄って聞いたことはあるけど、どうやるの?」「何に注意すればいいの?」
今回はそんな疑問にお答えするため、相続放棄の基本的な仕組みから、手続きの流れ、注意点までをわかりやすくご紹介します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)のプラス・マイナス両方の財産をすべて放棄し、最初から相続人でなかったものとみなされる制度です(民法第939条)。相続放棄を行うと、その相続人としての立場は他の人に移ります。
この手続きは、被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に、家庭裁判所へ申述しなければなりません(民法第938条)。この期間は「熟慮期間」と呼ばれ、原則として延長は認められません(例外あり)。
そのため、「放棄しようと思っていた」だけでは足りず、正式に家庭裁判所へ申し立てる必要があります。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄は、以下のような流れで進めていきます。
1. 財産の調査
相続放棄を行うかどうかは、財産の内容によって判断します。プラス・マイナス両方の財産を調べる必要があり、特に借金がある可能性がある場合は早急な調査が求められます。
2. 必要書類の収集
申述には、被相続人の戸籍や除票、申述者の戸籍などが必要です。関係性によっては追加書類が必要になることもあるため、不安な方は専門家に相談されることをおすすめします。
3. 相続放棄申述書の作成・提出
必要書類をそろえたら、裁判所指定の様式に沿って「相続放棄申述書」を作成します。これらを、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ提出します。この申述書は裁判所のホームページに書式がございますので一度ご覧ください。
提出後、「照会書」という確認書類が家庭裁判所から届きますので、内容に回答し、早めに返送しましょう。
4. 相続放棄受理通知書の受領
内容に不備がなければ、家庭裁判所より「相続放棄受理通知書」が送られてきます。これにより、正式に相続放棄が成立します。
相続放棄の注意点
相続放棄には、以下のような重要な注意点があります。
- プラスの財産も受け取れなくなる
相続放棄をすると、預貯金や不動産などの資産も相続できなくなります。遺産分割協議への参加もできません。 - 財産の処分はNG
熟慮期間内に相続財産を一部でも処分してしまうと、「相続を承認した」とみなされることがあります(民法第921条)。ただし、すべての行為が処分に当たるわけではないため、判断に迷う場合はご相談ください。 - 次順位の相続人に地位が移る
相続放棄をした場合、その相続権は次順位の相続人に移ります。たとえば、父親が亡くなり、母と兄弟2人が相続放棄をした場合、祖父母や叔父叔母など、思わぬ人が相続人となることがあります。
特に被相続人に借金があった場合、これらの人々が借金を背負ってしまう可能性もあるため、相続放棄は「誰が次の相続人になるのか」まで考慮したうえで行うことが大切です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は「相続放棄」の基本的な仕組みと手続きの流れ、そして注意点についてご説明いたしました。
相続放棄は、借金を引き継がないための大切な制度ですが、誤った判断や手続きの遅れによって、思わぬトラブルにつながることもあります。
判断に迷ったときや手続きが不安なときは、お早めに専門家へご相談ください。
当事務所では、相続放棄に関するご相談を初回無料で承っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。