遺言書の書き方と効力とは? 自筆・公正証書など種類を司法書士が解説
皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅です。
これまで、相続が起こった後の手続きについてお話してきましたが、今回は趣旨を変えてみます。
(関連記事はこちら:相続手続っていったい何をするの?)
そもそも、ご自身の遺産を誰に渡すかを相続人間で話し合って決めると、相続人同士の人間関係や感情が絡み、遺産分割がまとまらず、結果として相続登記などの名義変更や相続税の申告が遅れるという事態を招く場合があります。
そこで、ご自身の遺産をどうしたいのかを、あらかじめご自身で決める手段として「遺言書を書く」という方法が有効です。
遺言書の効力とは?
遺言書を書くことで、法律に則って行える行為には以下のようなものがあります。
- 相続分の指定・指定方法の委託(民法第902条)
→ あなた自身で、誰にどの割合の財産を相続してもらうかを決めることができます。
例:配偶者と子供の2人が相続人の場合、法律上はそれぞれ2分の1ですが、配偶者に4分の3、子供に4分の1とする指定が可能です。 - 遺産分割の方法の指定・指定方法の委託(民法第908条1項)
→ ご自身の遺産を、ご自身が指定した方法で分割することができます。 - 遺産分割の禁止(民法第908条第1項)
→ 遺言書により、相続人間での遺産分割の話し合いを行わず、あなたが定めた方法でのみ遺産を分割することが可能です。(ただし禁止期間は最長5年間ですので、相続人は5年間後には遺産分割協議を行うことができます。) - 遺言執行者の指定・指定方法の委託(民法第1006条1項)
→ 遺産分割協議などでどの遺産が誰に取得されるか決まった後、事務的な手続き(例:不動産の名義変更)を行えない相続人に代わり、信頼できる第三者(遺言執行者)に任せることができます。
※よくあるケースとして、配偶者が既に亡くなり、相続人は子供だけだが、その子供が認知症などで手続きを行えない場合が挙げられます。
以上が、生前に遺言書を書くメリットとなります。
遺言書の種類
遺言書には、普通方式遺言と特別形式遺言がありますが、ここでは世間でよく言われる「普通方式遺言」についてご説明します。普通方式遺言は、以下の3種類に分かれます。
① 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、その名の通り、遺言者が全文を自筆で書く遺言書です。
遺言書に何を書かなければならないかは法律で定められており、その要件を満たさないと遺言書として認められません。
【自筆証書遺言】
第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 (省略)
3 (省略)
自筆証書遺言は、手軽で費用も安く済みますが、以下のデメリットがあります。
- 遺言書を紛失しがち
- 相続人が勝手に開封し、検認の手続きが必要になる場合がある
- 相続人に見つけられない可能性がある
- 改ざん、書き換え、または隠されるリスクがある
② 公正証書遺言
公正証書遺言は、次の要件を満たす必要があります。
【公正証書遺言】
第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 証人2人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言は、証人を2人用意するのが必要であり、民法第974条により相続人が証人になることができません。そこで弁護士や税理士、司法書士などの専門職が遺言書の作成サポートを行い、その流れで証人になることがほとんどです。
そして、専門職がどんな遺言にしたいかを聞き取りしたうえで、文案を作成し、それを公証人が確認し、最終文案を公証人が作成します。そのため法律上誤った記載がされることが少なく、さらに原本が公証人役場に保管されるため、検認手続きが不要で、改ざんのリスクもほぼありません。
③ 秘密証書遺言
最後に、秘密証書遺言についてご説明します。実際に運用されるケースは少ないですが、内容を知られたくない方に適した方法です。
【秘密証書遺言】
第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。一 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
二 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
三 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
四 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
秘密証書遺言は、手書きの遺言書本体を封筒に入れ、その封を公証人と証人が署名・押印することで、内容が知られないように作成されます。しかし、公証人への手数料、証人の確保、遺言書発見されないことのリスクなど、実務上のハードルがあるため、あまり利用されることはありません。
以上が、遺言書の効力および3種類の普通方式遺言の要件となります。生前に遺言書を書くことは、相続が発生した後の混乱を回避し、あなた自身の意思を確実に伝えるための有効な手段です。
次回のブログでは、特別形式遺言についても軽く触れさせていただければと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次回のブログでお会いしましょう。
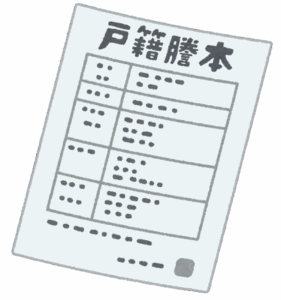

“遺言書の書き方と効力とは? 自筆・公正証書など種類を司法書士が解説” に対して2件のコメントがあります。