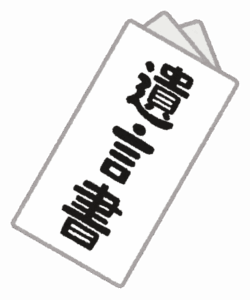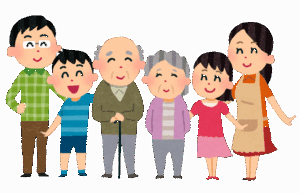相続登記の義務化とは? 2024年施行の新制度を司法書士が解説」相続登記の義務化について
こんにちは。司法書士の竹本海雅です。
皆さんは、「相続登記が義務化された」という言葉を耳にされたことはありませんか?
令和6年4月1日より、不動産登記法が改正され、相続による所有権移転登記については、相続開始から 3年以内に登記を行うことが義務 となりました(新不動産登記法第76条の3)。これは、それまで原則として任意であった権利部の登記の例外となる、非常に重要な改正です。
昨年の春頃から、街中でも「相続登記義務化」といった広告を目にすることが増え、多くの方が相続登記に関心を持つようになったと感じています。
では、実際に「相続登記をしないとどうなるのか?」
今回は、そのリスクやデメリットについて分かりやすくご説明いたします。
相続登記をしないとどうなるのか?
相続登記を怠ると、主に以下の3つの大きなデメリットがあります。
1. 不動産の売却ができなくなるおそれ
相続登記をしていないと、いざ不動産を売却しようと思っても、その手続きができなくなる可能性があります。
不動産取引では、司法書士による厳格な本人確認が求められます。登記簿に記載されている名義人と実際に売買の場にいる人が一致しなければ、登記申請が却下される可能性があるのです(不動産登記法第25条)。
登記名義人が亡くなっていて、自分が正当な相続人であっても、登記手続きがなされていなければその権利は証明できません。
結果として、買主が見つからなかったり、せっかく売却の話がまとまりかけても、登記が通らず契約が白紙になることも起こり得ます。
2. 払わなくてもよい固定資産税を負担し続ける可能性
亡くなった方名義の不動産にも、当然ながら固定資産税が課されます。
相続登記をしていない場合、その不動産は相続人全員の法定相続分に基づく共有財産となり、固定資産税も連帯債務となります。つまり、相続人の一人に対して税額の全額が請求されることもあるのです。
さらに、遺産分割協議を行っていない状態で相続人の一人(たとえばAさん)が借金をしていた場合、債権者はその不動産の法定相続分に相当するAさんの持ち分を差し押さえ、競売にかけることが可能になります。
このようなトラブルに発展する可能性を未然に防ぐためにも、早期の登記が重要です。
3. 相続手続きがどんどん複雑になる
相続登記を放置すると、次の世代へと相続が重なり、いわゆる「数次相続」が発生します。
そうなると、相続人の数が増え、連絡を取ったことのない親族や、居場所がわからない方とも連絡を取らなければならなくなります。連絡がつかない相続人がいる場合、家庭裁判所を通じた手続きが必要になることも。
また、「相続人が誰か」を確定させるために、大量の戸籍を収集しなければならず、その労力や費用も相当なものです。
相続手続きは、早めの対応がカギ
以上のように、相続登記をしないことで生じるリスクは少なくありません。
それぞれのケースにより異なりますが、登記を怠ったことによって問題が拡大することも多々あります。
亡くなった方の相続が発生したら、できるだけ早い段階でご家族間で話し合い、必要な手続きを進めることを強くおすすめします。
専門家への相談も選択肢のひとつ
相続登記はご自身でも可能ですが、専門知識が必要な部分も多く、判断を誤ると思わぬトラブルに発展することもあります。
不安な点がある場合は、弁護士・税理士・司法書士といった専門家へご相談いただくことで、スムーズかつ確実に手続きを進めることができます。
「トラブルを未然に防ぐ」ことも、私たち専門職の大切な役割だと思っております。
今回はここまでです。
相続登記の義務化を機に、ご家族の未来のために一度見直してみてはいかがでしょうか。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次回のブログでお会いしましょう。