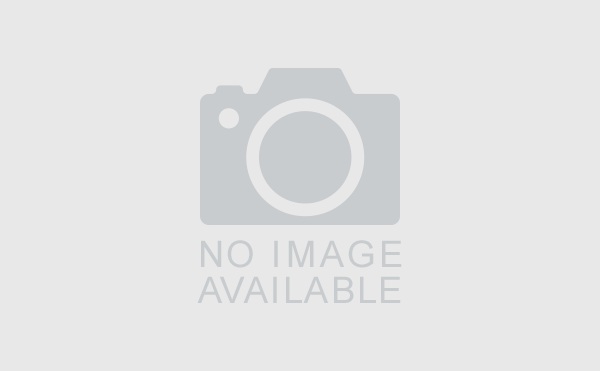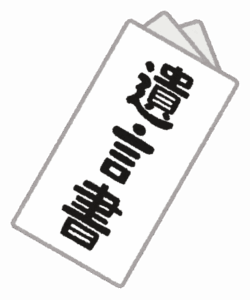相続手続の流れとは?戸籍収集から名義変更まで司法書士が解説
こんにちは。司法書士の竹本海雅です。
前回のブログでは、「相続手続をしなかったらどうなるのか?」についてお話しました。
今回は、実際に相続手続ではどのようなことを行うのか、「なんとなく知っているけど、ちゃんとはわからない」という方に向けて、丁寧に解説していきます。
相続とは何か?
まず、相続手続の話に入る前に、「そもそも相続とは?」という制度の基本から触れてみましょう。
相続とは、一般的には「亡くなった人の財産を引き継ぐこと」とされていますが、民法第896条では以下のように定められています。
(相続の一般的効力)
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
ここで重要なのは「権利義務」という言葉。
つまり、亡くなった人が持っていた**遺産(プラスの財産)**だけでなく、**借金などの義務(マイナスの財産)**も引き継ぐ、ということです。
このように、相続は必ずしも“得”とは限らず、状況によっては“負担”になることもあるため、注意が必要です。
誰が相続人になるのか?
相続人が誰になるかは、民法によって明確に定められています。
まず、常に相続人になるのが配偶者です。
そのうえで、次のような優先順位で他の相続人が決まります。
■ 民法の規定(一部抜粋)
(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。
(子及びその代襲者の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
子が先に亡くなっている場合は、その子(=孫)が代襲して相続人となる。
(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第889条 被相続人に子がいない場合は、直系尊属(父母など)、
それもいない場合は兄弟姉妹が相続人となる。
■ 相続の順位
- 配偶者:常に相続人
- 第1順位:子(または孫)
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹(または甥・姪)
このように、配偶者に加えて、誰が“他の相続人”となるかは、被相続人の親族の状況により変動します。
代襲相続とは?
ここで登場するのが「代襲相続」という制度です。
これは、元々相続人となるべき人が亡くなっていた場合に、その子(つまり孫や甥姪)が代わりに相続人となる制度です。
例:
- 被相続人の子が既に死亡していた → 孫が相続人となる
- 被相続人の兄弟姉妹が死亡していた → 甥・姪が相続人となる
このようなケースでは、相続人の調査が非常に複雑になりやすく、
「相続人が自分であることを知らない」「連絡が取れない」という問題が生じやすくなります。
相続手続の最初の一歩:戸籍の収集
相続手続において、最初にすべきことは相続人の確定です。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人を全て把握する必要があります。
なぜこれが重要かというと、遺産分割協議が有効に成立するには、相続人全員が協議に参加していなければならないからです。
遺産分割の方法
相続人が確定したら、次に「財産をどう分けるか」という遺産分割の話し合いを行います。方法は次の3つ。
① 遺産分割協議
相続人全員での話し合い。最も一般的な方法。
② 遺産分割調停
相続人間で合意ができない場合、家庭裁判所に申し立てて、裁判所の調停を交えて話し合う方法。
③ 遺言書による分割
被相続人が有効な遺言書を遺していた場合、その内容に従って分割します。
財産の名義変更手続き
遺産分割が決まった後は、それに基づき名義変更等の具体的な手続きを行います。
例として以下のような手続きがあります:
- 不動産の相続登記(法務局で)
- 預貯金の払い戻し
- 株式・保険などの名義変更
- 車の名義変更
- 保険の解約・受取手続き など
結びに
ここまで見てきたように、相続手続は「人間関係」と「法律手続」が絡み合う複雑な作業です。
家族仲が良くても、遺産分割で思わぬトラブルが生じることもあります。
そこで、**相続トラブルを未然に防ぐ方法の一つが「遺言書を遺しておくこと」**です。
次回のブログでは、この「遺言書」について詳しくお話ししたいと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次回のブログでお会いしましょう。