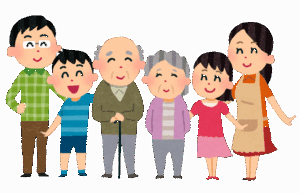成年後見制度をもっと詳しく!【札幌 あいの里 司法書士】
皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅です。
前回は成年後見制度の歴史とその概要についてお話ししました。
今回は、そんな成年後見人についてもっと深堀してお話ししてみようと思います。
成年後見人が選任されるまで
前回のブログでもお伝えしたように成年後見人には、①法定後見人と②任意後見人の2種類ありますが、具体的にどのように選任されるのでしょうか?
まず法定後見人は、本人やその親族から家庭裁判所に対して申立てを行うことから始まります。この申し立ては認知症を患っているなどの理由で実際に判断能力がなくなった後に行われるものです。その際に必要になる書類としては、例えば後見人選任申立て書や医師の診断書、本人の戸籍謄本、本人の財産状況を証明する通帳のコピーなどが挙げられます。これらを携えて家庭裁判所に選任申立てを行います。
その際に、後見人等候補者事情説明書という書類を提出することにより、「この人を後見人にしてほしいです」という要望を出すことができ、家庭裁判所が審査して裁判所が認めたらその後見人等候補者事情説明書に書かれた人が晴れて後見人となります。
ただ、実際に親族などが後見人等候補者になった場合では相続の関係などで認められないこともありますので、弁護士や司法書士などの専門職が後見人に就任するのが一般的となっていますが、例えば財産管理だけを専門職に後見人としてやってもらうという利用の仕方もございますのでそこはそれぞれの事情に応じて選択することができます。
一方で任意後見人についてなのですが、これは本人がまだ判断能力がしっかり残っていることが前提となっている制度となります。
何故かといいますと、これは本人と将来後見人になってほしい方(Aさんとします)との間の「もし自分が認知症になったときに後見人になってくださいね」という「契約」となっております。
契約であるということは、本人とAさんの間でしっかりと契約内容を理解し、合意を取るという流れを取る必要があります。なので認知症などですでに判断能力が怪しい場合は任意後見契約そのものが成立しない可能性があります。
何故かといいますと、この契約は公証人よって作成される「公正証書」によって作成される必要があります。その際に結構公証人から様々なことを聞かれるのですが、そこできちんと答えれなかったりすると、そもそも公証人の判断によっては契約書が作られないこともあります。契約内容を当事者が理解していない以上、回答も曖昧になってしまいますからね。
いかがでしたでしょうか。今回は成年後見人がどのような流れで選任されるのかについての概要をお話ししました。
なかなか仕事内容についてお話しできないですが、これはこれですごく内容が濃くなってしまい1つのブログでは収まりきらないので、分けてお話しさせていただきます。
では、今回はここまで。また次回のブログでお会いしましょう。