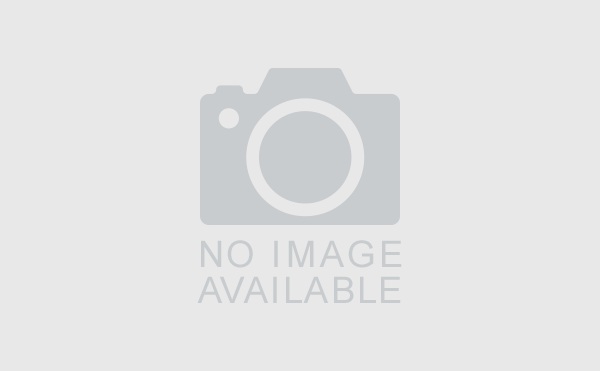家族を守るために――成年後見制度とは何かについて司法書士がわかりやすく解説!
皆さま、こんにちは。司法書士の竹本海雅です。
今回は「成年後見制度」についてお話ししたいと思います。
成年後見制度の歴史を少しだけ
まず最初に、成年後見制度の成り立ちについて、少しだけご紹介します。
現在の成年後見制度ができる前には、「禁治産・準禁治産」という制度が存在していました。これは明治31年に施行されたもので、認知症や精神疾患などによって判断能力が低下した方の財産を管理することを目的とした制度です。この制度では、禁治産者には「後見人」、準禁治産者には「保佐人」が付けられていました(この「後見人」「保佐人」については後ほど詳しくご説明します)。現在の制度にもこれらの用語が残っていることからもわかるように、基本的な役割には共通点も見られます。
しかしながら、この旧制度には多くの課題がありました。たとえば、夫婦の一方が制度を利用する場合には、必ず配偶者が後見人(または保佐人)にならなければならなかったこと。また、後見人は一人しか選任できない仕組みだったこと。そして何より大きな問題は、「禁治産」や「準禁治産」の宣告を受けると、その事実が戸籍に記載されてしまう点でした。これは、制度の利用者に対する差別や偏見を助長し、本人の人権を大きく侵害するものでした。
こうした背景を踏まえ、平成11年に旧制度は廃止され、現在の成年後見制度が創設されることとなりました。
制度の大きな変更点
新制度には、いくつかの大きな変更点があります。主なものは以下のとおりです。
- 「禁治産・準禁治産」という用語が廃止され、「被後見人」「被保佐人」などの新しい用語が導入された
- 新たに「補助人」という制度が設けられた
- 複数後見制度(複数人での後見)を導入
- 後見に関する情報が戸籍に記載されないようになった
これらの変更の背景には、超高齢社会の進展や、国際的な福祉の価値観の変化があります。たとえば、障害のある方も可能な限り地域社会で暮らしていけるようにしようという理念や、介護福祉のあり方が「行政による措置」から「利用者と施設の契約」にシフトしてきたことなどが挙げられます。
その結果、単に財産を管理するための制度ではなく、「本人の意思を尊重し、権利を擁護しながら支援する制度」へと、大きく変わったのです。
成年後見制度の概要
成年後見制度は、大きく分けて次の2種類があります。
- 法定後見制度
- 任意後見制度
法定後見制度について
法定後見制度は、すでに本人の判断能力が失われている場合(認知症などが典型例です)に、家庭裁判所に申し立てることによって開始される制度です。この制度には、本人の判断能力の程度に応じて、次の3つの類型があります。
- 成年後見人:本人の判断能力がほとんどなく、日常生活や財産管理を自分で行うことが難しい場合に選任されます。
- 保佐人:判断能力が一部あるものの、重要な契約等を行うには著しく不十分とされる場合に選任されます。
- 補助人:基本的な判断は可能であるものの、判断能力が一部不十分で支援が必要とされる場合に選任されます。
これら3つの類型は、それぞれ後見人の権限の範囲やできることが異なります。この違いについては、また別のブログ記事で詳しくご紹介したいと思います。
ここでは、「法定後見には3つの種類があり、本人の状態に応じて使い分けられている」ということだけ押さえておいていただければ大丈夫です。
任意後見制度について
任意後見制度は、本人の判断能力がまだ十分にあるうちに、「将来自分の判断能力が不十分になったときに備えて、誰に後見をお願いするか」を決めておく制度です。これは、本人と後見人になる予定の人との契約によって成り立つ仕組みです。
任意後見契約は、公正証書で作成される必要があるため、公証役場で正式に手続きを行います。実際にその後、本人の判断能力が低下した際には、家庭裁判所が選任する後見監督人のもと、任意後見人が活動を開始することになります。
おわりに
いかがでしたでしょうか。今回は、成年後見制度の全体像と、法定後見・任意後見の違いについてご紹介しました。
次回のブログでは、実際に後見人がどのような役割を担うのか、具体的な内容についてお話しできればと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。また次回のブログでお会いしましょう。