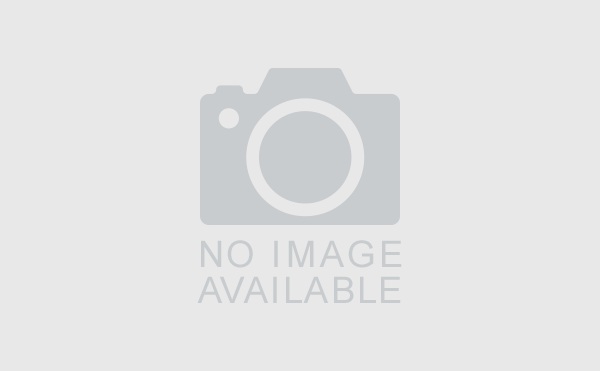個人事業主の法人成りについて司法書士が解説します(札幌)
皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもとかいま)と申します。
世間一般的に、個人事業主の方が会社を作り、その事業を法人単位で行うことを法人化と言います。これは主に結果的に法人化したほうが所得税の節税になるがあるため、それ目的でおすすめされることがあります。
ただ、実は法人化が相続対策にもなることをご存じでしょうか。今回はそのことに関してのお話です。
法人化するメリット
法人化する最大のメリットとしては、不動産評価の基準が変わることにあります。具体的な事例を用いて解説します。
法人化の事例
父は個人事業として飲食店を営んでいます。飲食店の店舗及び土地は、父が数
年前に購入したもので、名義は全て父名義となっています。今後の相続対策とし
て法人成りを薦められましたが、どのような効果があるのでしょうか。
(財産内容)
・店舗の固定資産税評価額 1,000万円
・土地の自用地としての相続税評価額 3,000万円
・借家権割合 30%
・借地権割合 70%
・賃貸割合 100%
個人事業主が法人成りにより会社を設立し、その事業を法人に引き継がせます。店舗や土地は事業用不動産として父名義のままにして、その法人に賃貸した場合(これが対策となります)、家屋は「貸家」、土地は「貸家建付地」としての評価となり、相続税の軽減対策となります。
もし、法人成りしなかった場合、評価は次のようになります。
1,000+3,000=4,000万円
一方で法人成りした場合は次のようになります。
① 土地………貸家建付地として評価(評基通26)
3,000-(3000 × 0.7 × 0.3 × 10)=2370万円
② 家屋………貸家(評基通93)として評価
1000- (1000 × 0.3 × 10)=700万円
①と②を足すと合計で3070万円となり、約1000万円ほど評価を下げることが出来ました。
法人化して自身名義の不動産を事業用不動産として賃貸することによって、不動産の評価を下げることになり、結果として相続税の軽減対策とつながるのです。
法人化に向けた手続きとは
ここからは、法人化に向けて、どのような手続きを取るべきなのかについてお話していきます。
一般的に、法人化とは会社を作ることを意味します。そして、会社というのは株式会社であれ、合同会社であれ、その他の法人であれ、「登記」をすることによって会社を設立することになります。
ここでは、株式会社を設立する場合に焦点を当ててお話ししていきます。
具体的には下記のような手順で手続きが進んでまいります。
会社を設立しようと思っている人のことを法律上「発起人」と言います。その発起人が定款という会社の根本的なルールを作り(これを定款を言います。)、その全員が記名・押印をしなければなりません。
発起人は株式を必ず持たないといけません。そして、定款作成の段階で株式をどれくらい発行して、株式を持つのかについて決めておくことが一般的です。
そして、会社設立に際して、定款を公証人によって認証を受ける必要があります。
定款の作成が終わったら、各発起人全員が引き受けた株式についての金銭の払い込みや財産の給付を行います。金銭の払い込みは、発起人の定める銀行等で行います。これは、定款の認証前の払い込みもできます。
出資まで行ったら最後は登記の申請を行います。登記の申請に必要な書類は以下の通りです。
登記の申請を行うことで、会社の設立となります。
- 登記申請書
- 登録免許税納付用台紙
- 定款
- 発起人の決定書
- 設立時取締役の就任承諾書
- 設立時代表取締役の就任承諾書
- 設立時取締役の印鑑証明書
- 資本金の払込みがあったことを証する書面
- 印鑑届出書
- 「登記すべき事項」を記載した書面又は保存したCD-R
①の定款の作成について、詳しくお話しします。
定款の作成に際し、何でもかんでも規定していいんですよね。ただ、必ず決めないといけない事柄がございます。それは以下の通りです。
・目的
・商号
・本店所在地
・設立に際して出資されている財産の価額又はその最低額
・発起人の氏名又は名称及び住所
以下順番にお話ししてみます。
目的
会社というのは、目的に記載された事項について権利及び義務を負うとされています。つまり、その会社でどのような事業を行いたいのかについて、目的事項として記載しておかないと会社事業として主張することが出来ません。
また、建設業などのようにその事業を行うために、行政の許可が必要な事業を行うためには単に建設業と書くだけでは認められないこともあります。
商号(会社名)
当然ですが、会社名を書かないことには何も始まりません。ただ、1つだけ制約があります。それは同じ場所に同じ会社名があってはいけないということです。例えば札幌市○○に「A」という会社がある場合に、札幌市○○に「A」という会社を設立することが出来ません。これは類似会社による雲隠れを防ぐ趣旨です。
本店所在地
これは会社の拠点をどこにするのかについて決める必要があるということです。これは最小の行政区画まで決めておけばいいです。「当会社の本店は札幌市に置く」程度の記載で足ります。
ただし、登記申請をする場合は、地番まで記載することになりますので、要注意です。
設立に際して出資されている財産の価額又はその最低額
これは発起人が株をどれだけ発行してどれだけ引き受けるのかと関係してきます。例えば「300株のうち100株引き受けて10万円を金銭で出資します」みたいな感じです。
発起人の氏名又は名称及び住所
定款に記載された発起人は株式を引き受けます。つまり将来の株主となります。また、先に述べたように発起人が何株引き受けるのかについても実務上は記載します。
また、発起人についてはだれでもなることが出来ます。個人、法人、地方公共団体等発起人になるのに資格はございません。
定款について
定款について簡単にお話しします。
定款は会社上の根本となるルールでございます。そして、そこには発起人全員の署名又は記名押印が必要となります。
しかし、紙の定款の場合、印紙代として4万円かかってしまいます。さらに公証人への手数料を支払う必要がございます。そこで、定款の認証を行うためには、印紙代と手数料を支払わなければならず、費用が割高になってしまいます。
そこで、定款というのは紙での作成のみならず、ワードなどで作成しそこに電子署名をする方法を取ることにより、印紙代を節約することが出来るのです。実務上は電子定款を作成し、それをオンライン上で公証役場に提出することにより認証手続きを行います。そうすることによって、紙で定款を作るよりも安く作ることが出来ます。
最後に
いかがでしたでしょうか?今回は相続対策としての法人化のメリット及びその手続きについてお話をさせていただきました。
法人化による節税対策となると多岐にわたり非常に専門性が高いものとなっております。
法人化を検討されている方々は是非とも税理士等の専門家に一度相談していただけますと手続きもスムーズに進むと思います。
弊所でも、法人化に関する相談を承っております。
その際は、税理士等の専門家と連携して行って参りますので、ぜひご連絡いただけますと幸いです。