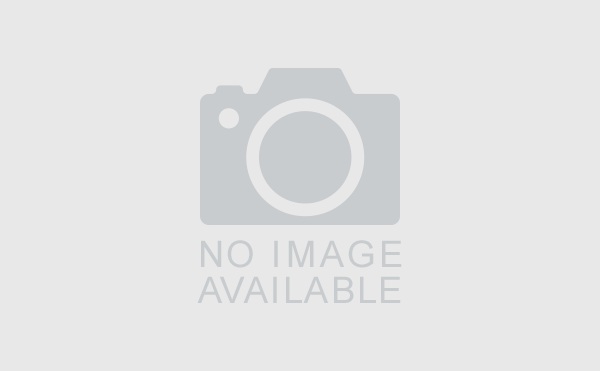遺言実現のために遺留分を放棄したい~リスクと方法について司法書士が解説~
皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもとかいま)です。
前回まで、相続への備えとして「「誰に・どんな財産を・どれくらい」渡すのかを決めておいて、遺言書を作成することが大切であるということをお話ししました。しかし、一方で兄弟姉妹を除く相続人には「遺留分」があるため、遺言書の内容が遺留分を侵害している場合、遺留分を侵害された相続人は、その分の金銭を請求することが出来ます。請求をするかしないかは相続人の自由でございますが、もし請求をした場合、この金銭をだれが負うのか、そもそも支払うことが出来るのかという別の問題に発展してしまう可能性があります。
詳細は以下のブログにございますので、ご覧いただけましたら幸いです。
そこで、民法の規定で相続が開始する前に家庭裁判所の許可を得ることで遺留分を放棄することによって、遺留分を気にすることなく遺言書を作成することが出来、極端な話「全財産を○○に相続させる」という内容の遺言書を作成することもできるのです。
遺留分放棄のメリットとリスク
遺留分を放棄することによるメリットとして一番大きいのは、「遺留分を気にすることなく」遺言書を作成することが出来るという点です。
一方で注意点やリスクがたくさんあります。それを列記させていただきます。
- 遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可がいる
- 遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てるのは、遺留分を有している相続人本人なので、本人が同意してないといけない
- 金銭的・手続き的負担がある
- 遺言書を紛失したり、無効になった場合に法定相続分によって相続することになる
以下、詳細にお話ししてみます
遺留分の放棄をするには家庭裁判所の許可がいる
申立書にその理由を記載するのですが、その内容を通じ「相続人本人の自由意思に基づいているのか」「そもそも放棄に合理的な理由があるのか」について家庭裁判所の方で判断します。場合によっては申立てを却下することもございます。
というのも、この制度は遺言書を書きたい人にとってはメリットですが、相続人にとっては遺留分という本来持っている権利を遺言者のために放棄することになりますので、相続人にとってはあまりいいことはないのです。
そこで、遺言者を書く側の圧力によって、遺留分を放棄してしまうことが起きる可能性があります。実際に「放棄の理由」の記載内容から強い干渉があったと推認されて申立てを却下された裁判例もございます。
また、「合理的な理由」としては、例えば、生前贈与や他の相続の時ににほかの相続人よりも多くの財産を取得していた場合が典型例となります。ただし、「合理性の有無」は総合的に判断されることになりますので、財産を渡していなかったとしても、両親が離婚してから全く交流がなかったケースでの遺留分放棄は不合理なものであるとは言えないとした裁判例もございます。
遺留分の放棄を家庭裁判所に申し立てるのは、遺留分を有している相続人本人なので、本人が同意していないといけない
これも先に述べた理由と重なるのですが、遺留分を有している相続人本人が自由な意思で申し立てる必要があるので、生前に贈与を行う等工夫を凝らす必要がある場合もございます。
金銭的・手続き的負担がある
遺留分の放棄を申し立てるには、収入印紙や郵便費用、添付書類となる戸籍の取得費用、代理人による申し立ての場合は代理人の報酬が必要となります。
申立てがされると審判が開始され、申立人は裁判所からの照会書に記載を求められたり、裁判所に出頭する必要があったりと手続き的な負担が発生します。
遺言書を紛失したり、無効になった場合に法定相続分によって相続することになる
個人的に最も厄介だと感じるのがこの問題です。
そもそも遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に認められる権利で、「最低限この部分だけは保障する」という趣旨のものであり、法定相続分とは別個の権利です。したがって、遺留分を放棄した人であっても、相続が発生した際には当然に相続権そのものは発生することになります。
そして遺言書によって相続分の指定や、特定の財産の分配方法を定めることができ、遺言の効力が法定相続分に優先するため、遺言者の希望どおりに財産の分け方を決めることが可能となります。
しかし、遺言書を紛失したり無効になってしまうと、原則どおり法定相続分に従った相続が行われることになり、遺留分を放棄した相続人も含めて遺産分割協議を行わざるを得ず、本末転倒な結果になってしまいます。
こうした理由から、実務上、公正証書遺言の作成が推奨されているわけです。
公正証書遺言の詳細はこちらのブログでお話ししております。
遺留分放棄許可申し立ての方法
⑴ 申立手続
遺留分放棄許可の審判の申立手続は以下のとおりです。
ア申立権者
遺留分権利者(兄弟姉妹以外の相続人)です。
なお、未成年者を代理して親権者である親が遺留分の放棄をする際、自分又は他の
子との関係で利益相反関係にある場合、特別代理人の選任が必要となる点に注意が必
要です。
イ 管轄裁判所
放棄しようとする相続の被相続人の住所地の家庭裁判所とされています(家事216①
二)。
ウ 申立てに必要な書類
家事審判申立書により申し立てます。添付書類として申立人及び被相続人の戸籍謄
本(戸籍記載事項証明書)、財産目録が必要となります。
エ申立費用
800円分の収入印紙、連絡用の郵便切手が必要となります
最後に
遺留分放棄は、遺言を自由に作成したい方にとって大きなメリットとなる一方、手続きやリスクも多く慎重な判断が必要です。実際に進める際には、ご自身の状況に合わせた適切なアドバイスを受けることをおすすめいたします。
「自分の場合はどうなのか」「どんな準備が必要なのか」など、少しでもご不安やご不明な点がありましたら、どうぞお気軽にご相談ください。