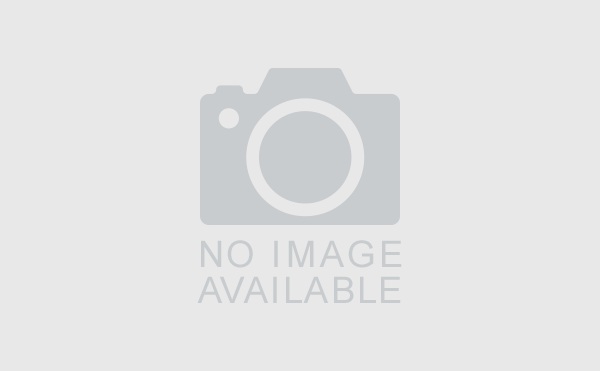直前期ですね
皆さま、こんにちは。司法書士の竹本海雅です。
今回は、少し「試験」の話もしてみようかと思います。
あくまでも「ブログ」ですからね(笑)
司法書士試験、直前期の過ごし方について
ご存じのとおり、司法書士試験は毎年7月の第一日曜日に行われます。
そして、その約3か月前にあたる4月〜6月は、いわゆる「直前期」と呼ばれる大切な時期です。
「直前期に何をすればいいか?」というのは、受験指導のプロである予備校の先生方にお任せするとして、今回は私自身がこの時期にどんなことをしていたのか、体験談としてお話ししたいと思います。
直前期、私は何をしていたのか
まず、私の受験歴ですが……実は6回、司法書士試験を受けました。
つまり、6回分の直前期を経験しているわけです(笑)
1〜2回目(専業受験時代)
最初の2年は大学生だったこともあり、授業には出ず(!?)、ほぼ専業受験生として朝から晩まで勉強していました。
具体的には、全科目のテキストと過去問を毎日ひたすら回す、いわば“皿回し”のような勉強法です。
ただ、この方法はかなりハードですし、今思えば効率的ではなかったですね。
一日に全科目を回すのは一見すごく効率がよさそうに思えますが、それぞれの科目にかけられる時間が少ないので、実際には周回数も少なくなってしまうんです。
それに、テキストを全部持ち歩いていたので、とにかく重い。重い割に成果が出ない方法でした(笑)
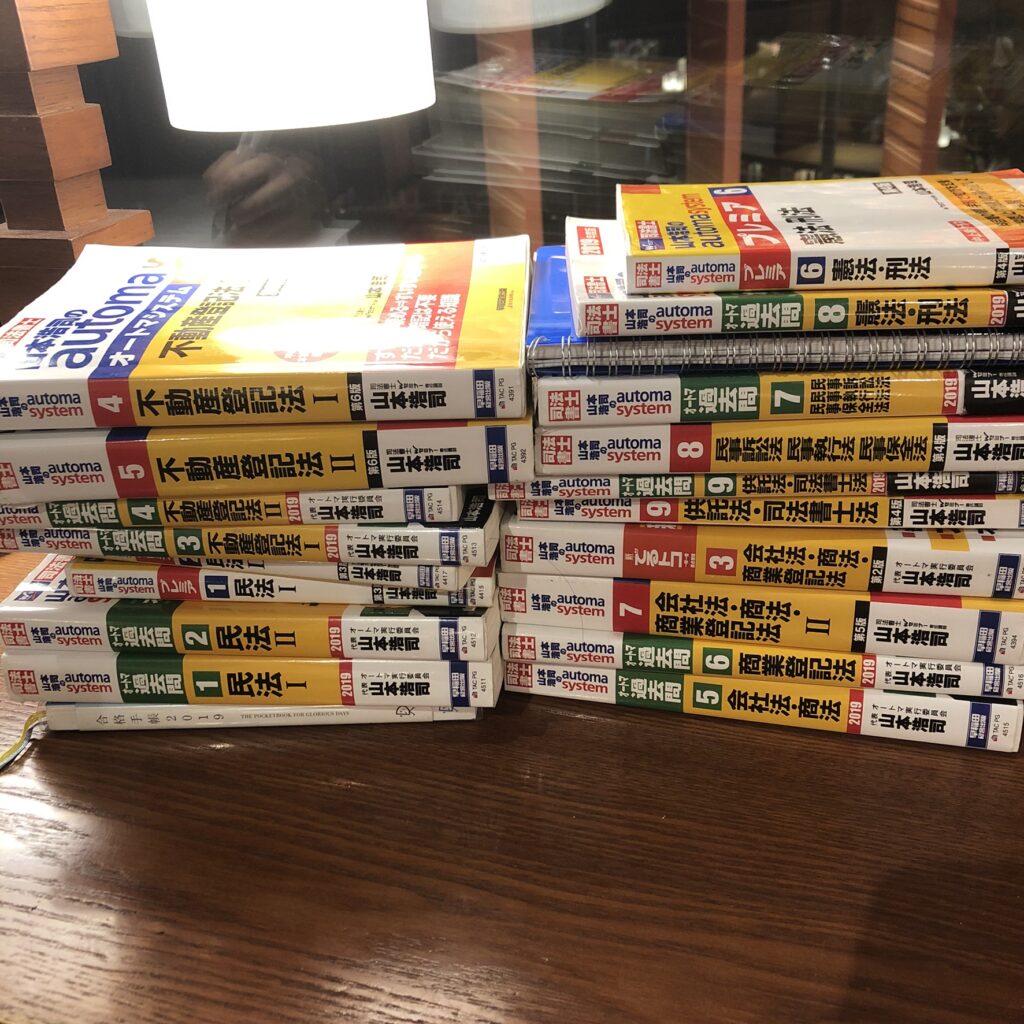
試験前日に勉強した教材です。
おそらく全科目分あるかと思います。
3〜4回目(勉強法に試行錯誤)
次の2年間は、効率を上げるために、11科目を2つのグループに分けて、テキストだけを重点的に回す方法に変えました。
結果として周回数は増えましたが、今度は「中身が頭に入ってこない」という別の課題に直面。
ここで痛感したのは、「ただ読む」「ただ解く」では意味がない、ということ。
本当に覚えないとダメなんです。ただの読書じゃ合格できません(笑)
この時期の経験から、私は「覚えたことを本試験で出せるかどうか」がすべてだということを学びました。
5〜6回目(合格に至った方法)
最後の2年で、ようやく自分の勉強法が固まりました。
じゃあ、「丸暗記したのか?」と言われると、そうではありません。
大事なのは、テキストに載っている情報を“思い出せる状態”にしておくことです。
人間は「思い出そう」と努力することで、脳が「これは大切な情報だ」と認識してくれる性質があります。
読書も勉強の手段のひとつですが、何度も読むよりも、何度も“思い出そうとする”ほうが効率的なんです。
某予備校でも推奨されている方法でテキストを読みながら、その先を思い出そうとする方法がありますね。私もテキストは違えど、似たようなやり方で勉強していました。
「質より量」ではなく「質も量も」
話は変わりますが、最後の1年は、派遣のアルバイトをしながら受験勉強をしていました。
それまでに比べて、明らかに勉強時間は少なかったですが、それでも合格しました。
なぜか?
それは、これまでに積み上げてきた「膨大な量」の勉強があったからです。
時間を測ったことはありませんが、ざっくり6000時間くらいは勉強していたと思います。
その中で、さまざまな方法を試し、反省し、自分なりの勉強スタイルを見つけることができました。
もちろん予備校のカリキュラムに沿うのは大事です。
でも、それに自分の工夫を加えて“自分専用のやり方”を作ることが、合格への近道だと私は思います。
とにかく、まずはやってみる。
何か理由をつけてやらないのではなく、とにかくやる。黙ってやる。
ちょっと極端かもしれませんが、「人間やめるくらい」がちょうどいいです(笑)
私の同期でも、真人間のまま受かった人はほとんどいませんでした。匙加減は大切ですが、それくらい必死にやらないと合格できない試験だと思います。
最後に
少し厳しいことも言いましたが、直前期は悔いのないように過ごしてほしいと思います。
正しい方向にたくさんの努力をすれば、合格できる試験ではありますので。
それでは今回はこのあたりで。
また次回のブログでお会いしましょう!