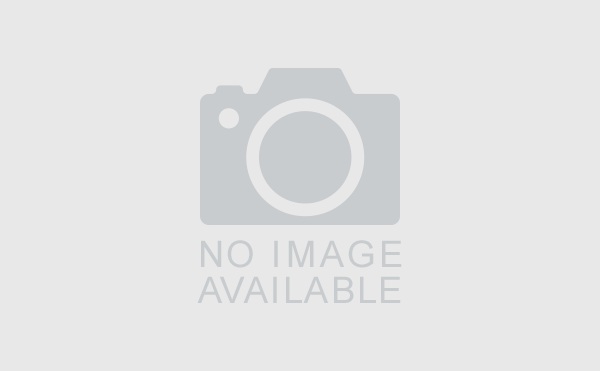相続発生前の対策シリーズ ①遺言書による対策(札幌 司法書士)
皆様、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもとかいま)と申します。
相続対策というのは多岐にわたっており、また、その有効性も現在の状況によって異なります。例えば、相続が発生してから遺言書を書いても全く対策にはならないというのは極端なお話ですが、これに近いものが様々な相続対策にございます。さらに相続対策と一言で言ってもそれについての情報が錯綜しているのが現実問題としてあるなと思うのが最近の雑感でございます。
そこで、今回から相続対策の種類とその有用性についてシリーズ化してお話ししてみようと思います。
今回から、遺言書による対策について取り上げてみます。
遺言書による対策
原則として、相続が開始すると、相続人は法定相続分に従って遺産分割協議を行います。しかし、亡くなった人がその生前、遺言書を作成すると、遺言書の効力が優先します。
つまり、遺言書を作成しておくことで、ご自身の財産を渡したい人に渡すことが出来るのです。
遺言書の効力とリスク
遺言書の効力として一番挙げられるのは、遺言書を作成することで、遺産分割方法や相続方法を指定したり、特定の財産を相続人や第三者に贈与することが出来ます。例えば、相続人間の仲が悪かったり、連絡がつかないというように遺産分割協議の成立が難しい状況にある場合に、遺言書を作成することで、相続人間の争いを防止することにつながります。
しかし、一方で注意点もいくつかございます。
例えば、有効な遺言をするには、遺言者に遺言能力が必要であります。例えば、15歳未満の人は遺言書を作成することが出来ません。さらに、以前のブログでも書きましたが、遺言書には3種類ございます。そして、それぞれ書き方が決まっております。この書き方に即した遺言書を書かないと遺言書が有効に成立しないということになります。
そして、特に気を使わないといけないのは遺留分の問題です。
遺留分とは、簡単に言いますと、相続人にはそれぞれ法定相続分とは別に、最低限、相続財産を確保することが出来る権利があり、それが遺留分と呼ばれているものです。具体的には被相続人の配偶者、直系尊属、子(子が亡くなっていた場合は孫)にこの遺留分があり、直系尊属のみが相続人である場合は被相続人の財産の3分の1、その他の場合は被相続人の財産の2分の1が遺留分となります。
なので遺言書を書いて相続分を指定することが出来るのですが、遺留分を侵害していた場合は、相続人が後になって遺留分を主張してきた場合、この遺留分の負担について、相続人間で争いの種になってしまう可能性があります。
また、遺言書を作成するうえで考えないといけないことがございます。
それは、財産を貰う人(受遺者と言います)が、遺言者より先に亡くなった場合です。この場合、亡くなった受遺者にわたる財産についての遺言は効力を失い、遺産分割の対象となります。こうなってしまいますと、その財産のために相続人が話し合いを行う必要が出てきて結果的に相続人間の争いの種になることにつながります。話し合いが成立するだけましで、全然連絡がつかないというような状況だったら、いつまでも財産分けが進まない可能性もございます。そういった意味でも注意が必要な対策となります。
遺言と税金について
当然のことながら、遺言書によって財産を贈与する(遺贈と言います)ような場合にも税金が発生します。なので、遺言書作成時においてはそのあたりの問題も踏まえたうえで財産の処分を決定する必要が生じます。
ここでは、簡単にその話をさせていただきます。
例えば、個人が財産処分に関する事項(不動産を相続人○○に相続させる等)を記載し、これによって相続人、受遺者が相続財産を取得した場合に相続税が課税されます。
さらに財産を貰った人が、配偶者、一親等の血族以外の者であった場合は、その者が負担する相続税は2割加算の対象となってしまいます。
また、相続人以外の者に不動産を贈与する場合は、不動産取得税が課税されたり、法人に贈与する場合は、対象財産が時価相当額で譲渡されたとみなされ、そこに含み益がある場合は遺言者に対しては譲渡所得税が課され、受遺者の法人に対しては法人税が課税されることになります。
このほかにも様々な観点で注意が必要な分野であり、税金は高度な専門性を有するので詳細は税理士にお問い合わせていただければと思います。
最後に
いかがでしたでしょうか。今回は遺言による相続対策についてお話してみました。遺言書を書くというのは相続対策の1つとして大変有効な手段ではありますが、それと同時に考えないといけない要素も多分に含まれていることが今回のブログを通じて伝わればと思います。
次回は、実際の遺言書を利用した対策を行った事例をご紹介できればと思います。
次回のブログでまたお会いしましょう