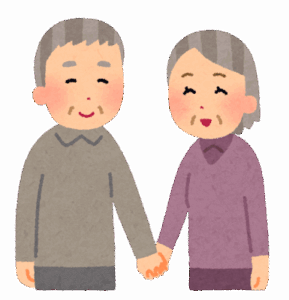相続人申告登記と行政書士による手続きについて【札幌市】
皆さま、こんにちは。司法書士の竹本海雅(たけもと かいま)です。
今回は、現在X(旧Twitter)上で司法書士の間で話題となっている「行政書士による相続人申告登記」について、その制度の概要と注意点をお話ししたいと思います。
相続人申告登記とは?
令和6年4月1日より、不動産の相続による所有権移転登記が義務化されました。同じくその日から新たにスタートしたのが「相続人申告登記」という制度です。
相続登記の義務化については以下のサイトをご覧くださいませ。
この制度は、相続人の一人が「私は○○の相続人です」と法務局に申出を行うことで、その不動産について相続人であることを公示できるというものです。これは、相続開始を知った日から3年以内に相続登記を行う義務が課せられたことへの、いわば“応急措置”的な制度です。
実際には、遺産分割協議が3年以内にまとまらないケースも多くあります。その場合、「法定相続による移転登記」を一旦行わなければなりませんが、この相続人申告登記を利用することで、それを省略しつつ義務を果たしたとみなされる点が大きな特徴です。
相続人申告登記のメリット
- 通常の相続登記に比べて必要書類が少なく、手続きが簡単です。
- 登録免許税が不要です。
- 登記義務を果たしたものと同等の扱いを受けるため、罰則の対象になりません。
- 相続人が複数いる場合でも、一人の相続人から申出をすることが可能です。
相続人申告登記のデメリット
- あくまで「仮の対応」であり、遺産分割協議がまとまった後には、再度相続登記を行う必要があるため、手続きが二度手間になる可能性があります。
- 第三者に主張するための登記ではないため、不動産の所有権を主張することが出来ません。
必要書類について
相続人申告登記を行うには、以下の書類を法務局に提出します。
- 被相続人の死亡が確認できる戸籍謄本
- 申出人が相続人であることを確認できる戸籍謄本
- 申出人の住民票
- 申出書(所定様式)
なお、①と②についてはケースによって必要書類が異なる場合があります。ご不明点がある場合は、ぜひお近くの司法書士にご相談ください。
行政書士がこの手続きに関与できるのか?
さて、ここからが本題です。
結論から申し上げますと、相続人申告登記は「登記申請手続き」に該当するため、行政書士が単独で行うことはできません。これは司法書士法に基づく業務範囲を逸脱する行為、いわゆる「非司行為」とされるものです。
最近、行政書士の方によるSNS上の投稿がこの点で誤った内容を含んでいたことから、司法書士の間でも大きな話題となりました。こうした誤解が広がると、制度の利用を検討されている皆さまにもご迷惑をおかけする恐れがあるため、今回のように改めて正しい情報をお伝えすることが大切だと考えています。
最後に
「登記」に関する手続きは、法的責任のもとで司法書士が担う業務です。皆さまの大切な不動産や相続に関わる問題に対して、正確で安心なサポートをお届けするため、ぜひ司法書士をご活用ください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。それでは、また次回のブログでお会いしましょう。