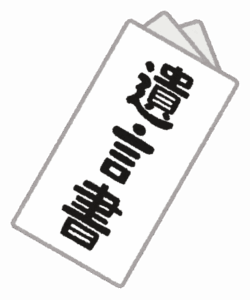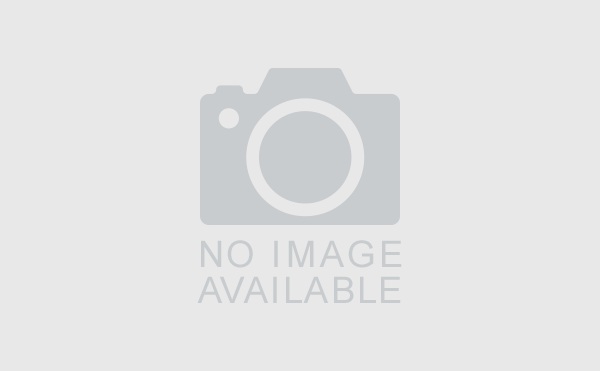遺言書を作成して成功した事例と失敗した事例(札幌 司法書士)
皆様、こんにちは。司法書士竹本海雅(たけもとかいま)です。
今回は遺言書を作成して成功した事例と遺言書を作成することで争いのもとになってしまった事例をそれぞれお話ししてみます。これはあくまでもモデルケースでございますが、実際どのように遺言書が活用するのか、失敗するのかについての実感を持っていただければと思います。
遺言の活用事例
妻と子供が法定相続人の場合
Aには、妻Bはいますが子供はいません。Aの両親は死亡していますが兄弟姉妹がC.Dの2人います。Aの財産は3000万円のABが住む自宅の不動産甲と現金が500万円あります。この事例において対策を取っておくとよいでしょうか
解説
1 法定相続分での取得
本事例において、先にAが死亡した場合、法定相続人は、配偶者であるB、C、Dとなり法定相続分は、Bが4分の3、CDが8分の1ずつとなります。具体的に言うとBは2625万円、CとDはそれぞれ437万5000円となります。
BがAの死亡後も自宅不動産甲に住み続けるため、甲不動産の取得を希望した場合、法定相続分を超える財産を取得することになります。そのため、CとDは500万円の現金の取得だけではなくBに代償金の支払いを求めることも予想されます。
そのため、遺産分割協議によってBは大証金の支払いのために不動産の売却を迫られたり、家は残ったものの今後の生活費を捻出できないという事態が懸念されます。
2 本事例における対応
そこで、本事例において、妻Bの生活を安定させるためにAが生前に「甲不動産を含む一切の財産をBに相続させる」という遺言書を作成しておくことが必要であると考えられます。兄弟姉妹には遺留分もないので、全財産を相続させることが出来るので有効な対策となるだろうと思われます。もし、CとDが子供だった場合は、遺留分を考慮する必要がありますので、現金500万円を有効活用して生前に贈与するなどして、遺留分侵害額請求をしないような施策を講じたり、生前にAがCとDと話し合っておく必要がございます。
遺言が紛争の種となった事案
Aには妻Bと子供がCDの二人います。
AはA及びBの体調が極めて悪く、夫婦二人で生活の維持が危うい状態となったことからDと協議し、ABの負担の下で自宅をリフォームして、D及びDの長男が2階で、ABが1階で別の生活を行うこと、およびA及びBがCとの交流を控えることを条件に、DがA宅に転居し、AB夫婦の生活の援助をしてもらうことになりました。
Aは自身の死後のBについて心配し、Dの支援によってBが平穏に生活できるようにと考えDの支援によってBが平穏に生活できるようにと考えその旨を付言事項に記載し、Aの相続においてCD間の相続分に関しDが有利になるような次の内容を記載した公正証書遺言を作成しました。
(1)土地建物に関する記載
自宅の土地建物をBに持ち分5分の3、Dに持ち分5分の2を相続させる。
(2)預貯金等に関する記載
①Bに下記の記載の預貯金を相続させる
○銀行 普通預金(口座番号○○○)
②Cには平成19年12月に相続時精算課税にかかる財産として1000万円を贈与済みである。
③Dに下記記載の預貯金を相続させる
□銀行 普通預金(口座番号□□□)
(3)その他
上記(1)(2)を除く被相続人の遺産は全部Bに相続させる。
なお、上記遺言書には「私がBより先に死亡した場合の遺言書」という文言が封筒の裏面に入っておりました。
この遺言を作成した後、先にBが死亡し、その後Aが死亡しました。Dは(2)③記載をもとに□銀行に対し、預貯金を相続したとして請求することが出来るでしょうか。
解説
1 本事例の特徴
Aは、自身の死後のDの支援によってBが平穏に生活できるようにと考え、C・D間の相続分に関しDが有利になるような遺言を作成しております。
遺言書の記載を見ると、この遺言はAが死亡したときにBが生存していることを前提としておりBがAの生前に死亡したことにより、前提が崩れてしまい、結果として遺言書の効力が失ったとみることが出来ます。
実際、同じ内容の自筆証書遺言書を残し、Dは遺言書の効力はあるとして銀行に対して支払い請求をした事例において、Cが遺言の効力を失ったとして裁判所で争うことになりました。(東京地裁令和2年7月13日判時2485.36)
2 裁判所はどう考えたのか?
結論から言うと、この遺言書は効力を失ったと判断されました。遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言だけを見て判断するのではなく、遺言書作成当時の事情や状況などを考慮して判断され、東京地方裁判所は、封筒に記載されている内容も遺言書の内容に含まれると判断されました。
3 本事例における対応
本事例ではおそらく上記の裁判例と同様の内容の遺言書が記載されていることで、封筒部分も遺言書と一部であると解釈される可能性が高いです。しかし、先にも述べたように遺言書作成当時の状況や事情を勘案した結果一体のものではないと判断される可能性もあります。
このように後になって遺言の効力を争うことになった原因は、BがAよりも先に亡くなった場合にどう遺産を分けるのかを遺言書に記載していなかったことです。前回のブログでも述べたのですが、財産をもらう側の人が遺言書を書いた人より先に亡くなると、原則として遺言書はその効力を失い、法定相続分による遺産分割協議を行う必要があります。
良かれと思って遺言書を書いた結果、その記載内容によって相続人間で争うことになり、お金と時間と精神面を削ってしまう結果となりました。
このような事態を防ぐために、Bが先に亡くなった場合の補充遺言も併せて記載しておくべきでした。
最後に
いかがでしょうか?今回は生前対策として遺言書を作成し、遺言書をうまく活用できた事例と逆に争いの種となった事例を紹介しました。
遺言書は生前対策として有効に機能する反面、その記載内容によってはうまく機能しないこともございます。
どのような内容を記載すれば、どのような効力が発生するのかについては高い専門性を有しております。
当事務所でも遺言に関する相談を承っております。何か相談したいことがございましたら、いつでもご連絡ください。
今回はここまで。また次回のブログでお会いしましょう。